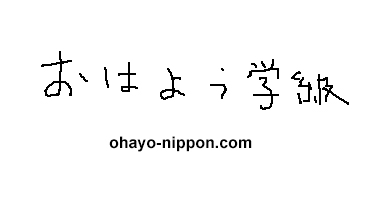「よそはよそ、うちはうち」
という言葉は子供を教育するうえで
よく使う言葉ですが、
ときに子供に使われることがあります。
僕も子供のころ、そう思っていたから、
子供たちはズル賢いよなぁ。
小学校の道徳の授業で
SNSを取り上げていた授業参観を
一度観たことがありました。
誹謗中傷や炎上、
インターネットネイティブ世代に
インターネットの怖さを
きちんと学校教育で伝えていて、
子供たちもそれを理解しているようで
とても感心した記憶があります。
こどもと向き合っていると、
ことインターネットに関しては、
子供たちの方がリテラシーが高いなと
思うことが多々あります。
なんていったって、
インターネットネイティブ世代なので、
閲覧だけでなく発信もするし、
コミュニケーションもすべて
インターネットでする世代です。
教育を受けていない大人たちの方が
その点において完全に弱者です。
ところがそんな弱者たちをも救うのが
インターネットの魅力でもあります。
多様性を成立させるためのツールなので、
インターネットは「何でもあり」が前提です。
それに対して教育するのは
なかなか難しいよな、、と思っていたのですが、
小学校の教育をみて、それは、
普通の人間社会のルールの教育と
何ら変わらないなと思いました。
電車の中でつばをはかないように、
上司に中指をたてないように、
弱いものいじめをしないように。
世界的にみたときに、
日本人はマナーがよいと
とても評価されます。
災害時などにも秩序を守り、
暴動もほとんど起きません。
そんな日本人もインターネット上だと
豹変してしまいます。
運転すると人が変わる、
みたいなものでしょうか。
であれば、教育に加えて罰を強化すれば
多様性の怖い部分は
もっと減っていくのかな。
プログラミングの条件式を
めっちゃ書きまくってガチガチに
縛りをつけるイメージとか?
僕も毎日ここに好き勝手書く
一人のインターネットユーザーなので、
いつか起こりうることだと思って、
考えさせられる問題です。
子供たちも教育はうけているけれど、
大人になるとどうなるか怖さはあります。
実際SNSいじめとかあるみたいだし。
嗅覚を鍛えて、嫌な臭いには近寄らない、
が、多様性の怖さに対しての
今のところの僕の考えです。
逃げ口がたくさん見つかるのも
インターネットのいいところだと思います。
今日も来てくれてありがとうございます。いよいよ学校生活が再開します。僕も出社になるかな。リアルが恋しいな。
20/05/25